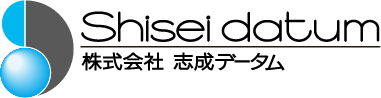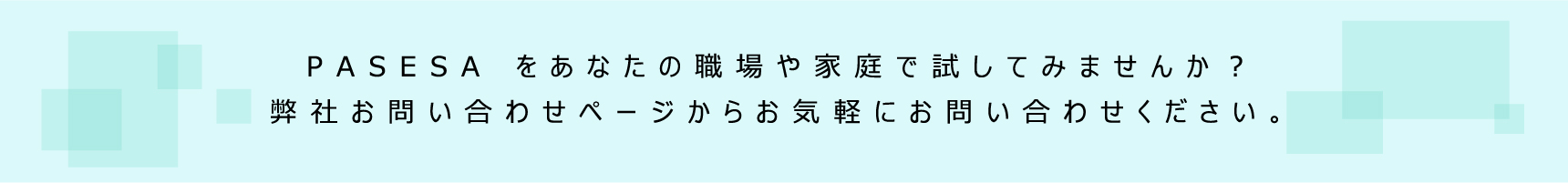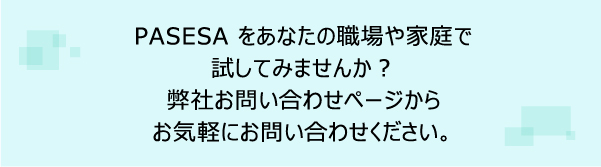blog
ブログ
健康診断などで「血圧が高めです」と言われる判定基準はどれくらいの数値か知っていますか?血圧の測定には二つの計測ポイントがあります。「上が◯◯◯、下が◯◯◯」なんて言いますよね。この「上」の値は、心臓が収縮して血液を全身に送り出す時の「最大血圧(収縮期血圧)」を指し、「下」の値が、心臓が拡張して血液を溜めている時の「最小血圧(拡張期血圧)」を指します。そして最大血圧が140mmHg以上、または最小血圧が90mmHg以上の場合、いわゆる「高血圧」と呼ばれています。血圧というのはその時々で変化しますから、たまたま少し高めだからといって「大変だ!」と慌てるのも性急です。とはいえ、高血圧が続くと血管や心臓に負担をかけることになるので、知らぬ間に動脈硬化が進んだり心不全のような病気の原因を放置していた!となりかねません…
それにしても、なぜ高血圧になってしまうのでしょう?
さまざまな要因が考えられますが、たとえば、よく言われるのが塩分(ナトリウム)の摂り過ぎです。人間の身体の中は水分と塩分が一定の濃度に保たれているため、塩分が増えるとそのぶん濃度を下げるため体内の水分も増えます。すると、血液量全体が増えてしまうため血管に与える圧力が増し、血圧が上がってしまう、と言われています。
その一方、日本人の食生活は塩分を多く摂りやすい、と言われています。お漬物やお味噌汁、醤油やソースなどの調味料、麺類の食事にも食塩がたっぷり使われます。ラーメンスープを全部飲むとそれだけで6g近い塩分を摂ってしまうことにも…。2016年の調査では、日本人の一日の食塩摂取量の平均値は約10グラム。WHO(世界保健機関)では、一日の目標値を5グラム未満に設定していますから、まずは「塩分控えめに」と言われるのも当然かもしれませんね。
次回は、高血圧と言われたなら心掛けたい、食生活の改善方法をご紹介します。